
従来の教育の枠を超え、3次元の仮想空間「メタバース」を活用する学校が急速に増えています。危険な実験を安全に行ったり、世界中の史跡へ瞬時に移動したり、あるいは不登校の生徒に新たな居場所を提供したり——。
本記事では、学習効果を劇的に高め、教育の可能性を広げる、国内外の学校教育におけるメタバースの具体的な実践事例を一挙にご紹介します。


日本国内の教育におけるメタバース活用事例
日本国内の教育現場におけるメタバース活用事例は「不登校・遠隔地支援」「体験型授業」「学校行事・広報」の3つの分野で活発に行われています。主な実践例を、学校の種類ごとにご紹介します。
角川ドワンゴ学園(N高等学校・S高等学校)
生徒にVRヘッドセットを配布し、仮想空間で授業や学校行事を実施しています。
単に映像を見るだけでなく、3D教材(例:VRで臓器のモデルを観察する、過去の史跡を歩き回る)に触れるなど、疑似体験に重点を置いた授業を展開しています。
また、VR空間での部活動や学校行事(バーチャル体育祭など)も実施し、全国の生徒が自宅から参加できる交流の場を提供することで、生徒間の交流を促進しています。
WAM高等学院
WAM高等学院では、通信制高校のサポート校として、生徒の学習環境とコミュニケーションの機会を創出するためにメタバースを活用しています。特に「登校しやすい居場所づくり」と「個別最適な学習の提供」を目的にメタバースプラットフォーム上に「バーチャルキャンパス」を開設。生徒は自宅からアバターでアクセスし、登校感覚で仮想空間にログインできます。現実の登校に不安を感じる生徒や、物理的に遠方に住む生徒に対し、心理的なハードルの低い「第三の居場所」を提供し、孤立を防いでいます。仮想空間内では、他の生徒や教員がアバターとして存在しており、気軽に声かけやチャットでのコミュニケーションが可能です。
メタバース塾KAI
メタバース塾KAIは「新しい学びの形」をテーマに、特に不登校の生徒や対面授業に苦手意識を持つ生徒、学習意欲を引き出したい生徒を対象とした、仮想空間のオンライン学習塾です。その実践例は「楽しさ」と「交流」を通じて学習のハードルを下げることに重点を置いています。
生徒はアバターとしてメタバース上の教室に入り、他の生徒や講師とリアルタイムでコミュニケーションを取ります。アバターがいることで、実際に教室にいるかのような「わいわい感」や「一体感」が生まれます。拍手をしたり、たまにアバターを動かして踊ったりする生徒もいるとのことです。自宅で一人で学習する従来のオンライン授業と異なり、他の生徒の存在を感じながら学べるため、孤独を感じにくくする効果があります。また、視覚的な刺激や対面に近い環境が、生徒の学習に対する積極性や意欲を引き出します。
メタバースを利用した不登校・教育支援
メタバースは、現実の学校になじめない生徒に「第三の居場所」を提供しています。以下に実践例を紹介します。

東京都「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム(VLP)」
不登校の児童・生徒や日本語指導が必要な児童・生徒のために、3Dメタバース空間を提供。カウンセラーや他の生徒がアバターで常駐し、ゲームなどを通して交流することで、子どもたちの孤立を防ぎ、社会性を育む支援を行っています。
登校が難しい生徒にも、自宅から授業や自習に参加できる機会を提供することで支援の輪を広げています。
佐賀県立太良高等学校
特に登校が難しい生徒や遠隔地にいる生徒に対し、学習機会と交流の場を提供することを目的として、メタバースを活用した授業(実証実験)を行っています。この取り組みは、文部科学省の指定研究などとも連携し「誰一人取り残さない新しい時代の高等学校教育」の実現を目指すものです。
生徒は各自で作成したアバター(自分の分身)を使い、インターネット上の仮想空間にあるクラスの「教室」に入室します。仮想空間の教室は、実際の学校の座席配置と同じように設定されており、対面授業に近い環境を再現しています。この空間では先生と生徒、生徒同士がリアルタイムでコミュニケーションを取ることが可能です。アバター同士が近づくと会話(ボイスチャット)ができる機能があり、まるでその場にいるかのように交流できます。教室の隣にグループワーク専用のスペース(個別の部屋)が用意されており、生徒はそこに移動してディスカッションに参加することもできます。
声で発言することに抵抗がある生徒でも、テキストチャットを使って質問や回答をすることができます。「声でるのは恥ずかしいから、チャットだと(質問などが)しやすい」という生徒の声もあるそうです。また、メタバース内の教室では、誰がどこにいるのかがアバターで一目瞭然なため、オンライン参加している生徒の出欠や授業への参加状況を把握しやすいというメリットがあります。
認定NPOカタリバ
認定NPO法人カタリバは「どんな環境に生まれ育っても、未来をつくりだす力を育める社会」を目指し、すべての10代の意欲と創造性を育む活動に全国で取り組んでいる団体です。
カタリバの活動は、主に以下の4つのテーマを軸に展開されており、困難を抱える子どもたちへの支援にも重点を置いています。
1、意欲と創造性の育成
大学生などの少し年上の先輩(「ナナメの関係」)が高校に出向き、生徒と本音で対話することで、生徒の進路や将来に対する意欲を引き出すプログラムです。高校生が自ら地域や社会の課題を発見し、解決に向けてプロジェクトを企画・実行する探究的な学びをサポートしています。
2、レジリエンス(心の回復力)の強化と居場所づくり
家庭環境や複雑な事情を抱える10代に、心の安心を届けるための居場所づくりや、学習・食事・体験活動を提供するプログラムです。オンライン不登校支援プログラムや、中高生の秘密基地「b-lab」などのユースセンター運営も行っています。また、メタバースを活用した不登校支援や、オンラインによる対話と創造的な学びの機会を提供するなど、デジタル技術を用いた支援も展開しています。
3、被災地における教育支援
東日本大震災(宮城県女川町、岩手県大槌町)や熊本地震などの被災地において、家を流され落ち着いて過ごせない子どもたちのために、放課後の学習と居場所づくりを兼ねた学校を設立・運営しています。災害発生時、現地の状況に応じて、学校再開支援、行政支援、物資の提供、居場所づくりなど、必要な教育支援を迅速に行っています。
4、地域・行政連携による教育改革
生徒が中心となり、教師や関係者と対話しながら校則・ルールを見直していく「みんなのルールメイキング」などの活動を通じて、学校の文化・運営の変革を支援しています。また、職員が自治体に出向し、探究授業の設計やカリキュラムマネジメントのサポートなど、教育行政そのものの変革を支援しています。
カタリバは、特定の学校や家庭だけでなく、社会全体で子どもを育む「新しい当たり前」をつくることを目指し、幅広い分野で活動している団体です。
高校・大学での実践例
新潟工科大学・長岡工業高等専門学校
キャンパス内の施設や実験装置を忠実に再現したメタバースオープンキャンパスを構築しています。遠方に住む受験生が、距離の制約なくキャンパス内の魅力を詳細に体験したり、教員と交流したりする広報活動に活用されています。
東京大学
2022年度に新入生歓迎会のオリエンテーションをメタバース上で実施するなど、大規模なイベントでの利用が進められています。
小学校での実践【鹿児島大学教育学部附属小学校】
全国で初めて、義務教育(小学校)の現場でメタバースを導入した事例です。授業の一部に活用し、子どもたちに新しい学習体験を提供しています。具体的には、総合的な学習の時間で、児童がテーマに沿った情報を集め、まとめた内容をメタバース空間内の展示場に発表・展示します。児童は自分でアバターを操作して、他のグループの展示スペースを巡回し、まるでバーチャルな発表会や美術館のように鑑賞します。発表だけでなく、他の児童の作品を自分のペースで鑑賞・評価し合うことで、より深く学習内容を理解する機会に。
また、離島など遠隔地の学校とメタバース空間で交流授業を実施。両校の児童がメタバースの同じ空間に集まり、お互いの地域の特色や文化を紹介し合ったり、テーマについて共同で話し合ったりする活動が行われました。
さらに一部の授業でVRゴーグルを使用し、高い没入感を伴う体験学習を取り入れました。例えば、VR内で世界の歴史的建造物や宇宙空間などを巡るバーチャル社会科見学を実施し、教科書や映像だけでは伝わらない「現場の雰囲気」を体感。この経験は抽象的な概念や遠い場所の情報を、直感的かつ具体的に把握できるようになります。
海外の教育におけるメタバース活用事例
海外では、主に大学レベルの専門教育とK-12(小中高)の体験型学習において、メタバースの活用が進んでいます。とくにVR技術を活用し、生徒がアバターで世界中の歴史的な場所や地理的な特徴を持つ場所へ移動し、まるでそこにいるかのような感覚で学習を行うことをバーチャル・フィールドトリップ(仮想社会見学)と呼び、近年注目を集めています。
バーチャル・フィールドトリップ
歴史・地理の授業で、エジプトのピラミッドや失われたマヤ文明の都市、人体の中など、物理的に移動が困難な場所へアバターで「社会見学」に行きます。学習内容の視覚化と没入感の向上が期待できます。また、記憶に残りやすい体験型学習を実現しています。
VictoryXR(メタバース大学)
仮想空間に「Metaversity(メタバーシティ)」を設立。VRゴーグルを配布し、学生がアバターで講義に参加。地理的な制約の解消と、VRによる高い没入感を持つ教育環境の提供を行っています。
スタンフォード大学
心理学の授業で倫理観や共感性の育成。単なる知識ではなく、「体験」として概念を理解させることに主眼をおいています。倫理観や共感性の育成、単なる知識ではなく「体験」として概念を理解させています。
オックスフォード大学
著名な教授による講義や資料をVR空間でアーカイブ化。仮想の学習室も提供し、学生が世界中からアクセスして学習できるようにしています。アクセシビリティの向上と、一流の教育リソースへの容易なアクセスを可能にしています。
科学実験・STEM教育
現実では危険な化学実験(例:爆発や有害物質の使用)や、高価な機器が必要な物理実験を仮想空間で安全に実施することができます。コスト削減と安全性の確保ができ、失敗を恐れず、何度も試行錯誤できる環境の提供を可能にしています。
職業訓練・企業研修への応用
ウォルマート (従業員研修)、ANA (飛行機整備士の研修)、JR東日本 (事故現場の再現研修)
でメタバースが活用されています。教育機関ではないものの、企業が研修・訓練にメタバースを取り入れている例は教育効果を示すものとして注目されています。
例えばANAでは、実際の航空機(例:エンジンや機体構造)をVR空間内に高精度で再現し、整備士がゴーグルを装着して仮想環境で整備作業の訓練を行います。通常の訓練では危険を伴う作業や、失敗が許されない複雑な手順を、VR空間で繰り返し安全に練習することができるメリットがあります。熟練の整備士が遠隔地から仮想空間に入り、訓練中の若手整備士を指導したり、実際の機材のデジタルツインを見ながら指示を出したりすることが可能になっています。
現実では危険な作業や、失敗が許されない専門性の高い実技を、仮想空間で何度も安全にシミュレーションして練習できるのがメタバースのメリットといえます。
海外ではメタバースを「高度なシミュレーション」と「アクセスを民主化するツール」として捉え、活用が進んでいることがわかります。
まとめ
教育現場でメタバースを実際に取り入れている事例は、日本国内でも海外でも非常に多様化しています。特に「不登校支援」「体験型学習」「遠隔地のハンデ解消」の3つの分野で注目されていることがわかりました。
メタバースは単なる「オンライン授業」の延長ではなく「体験による学習の深化」や「インクルーシブ教育の実現」を実践するものとして期待されています。メタバースは「誰一人取り残さない」という教育の理念を実現し、生徒一人ひとりの意欲と可能性を最大限に引き出す「新しい学びのプラットフォーム」として、今後も活用の幅を広げていくでしょう。
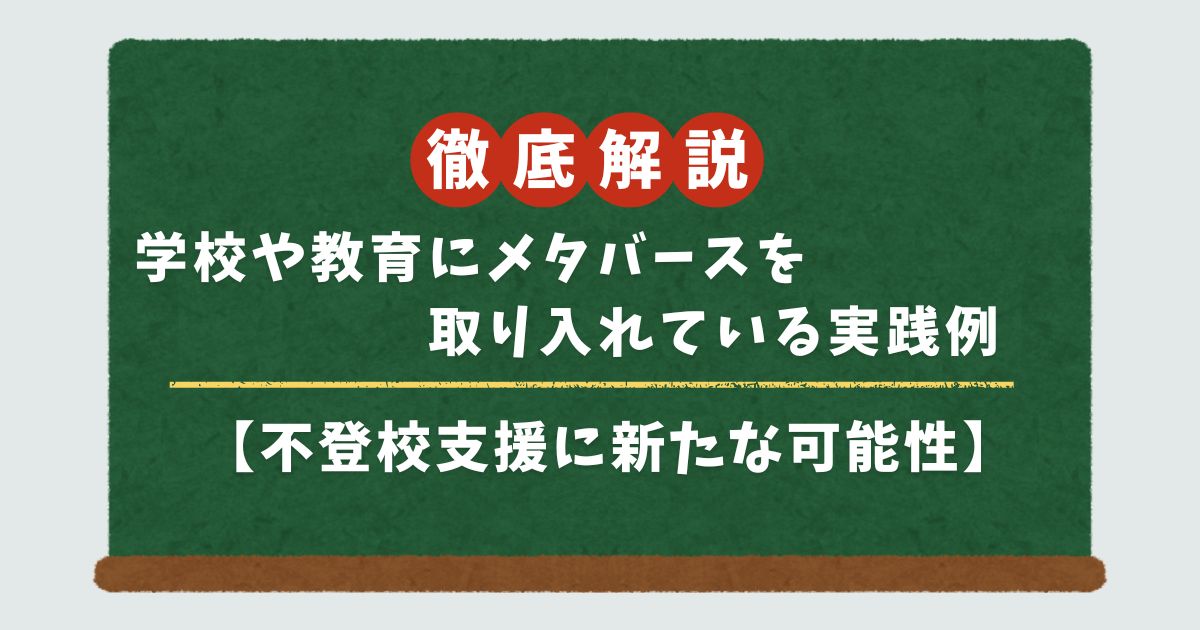
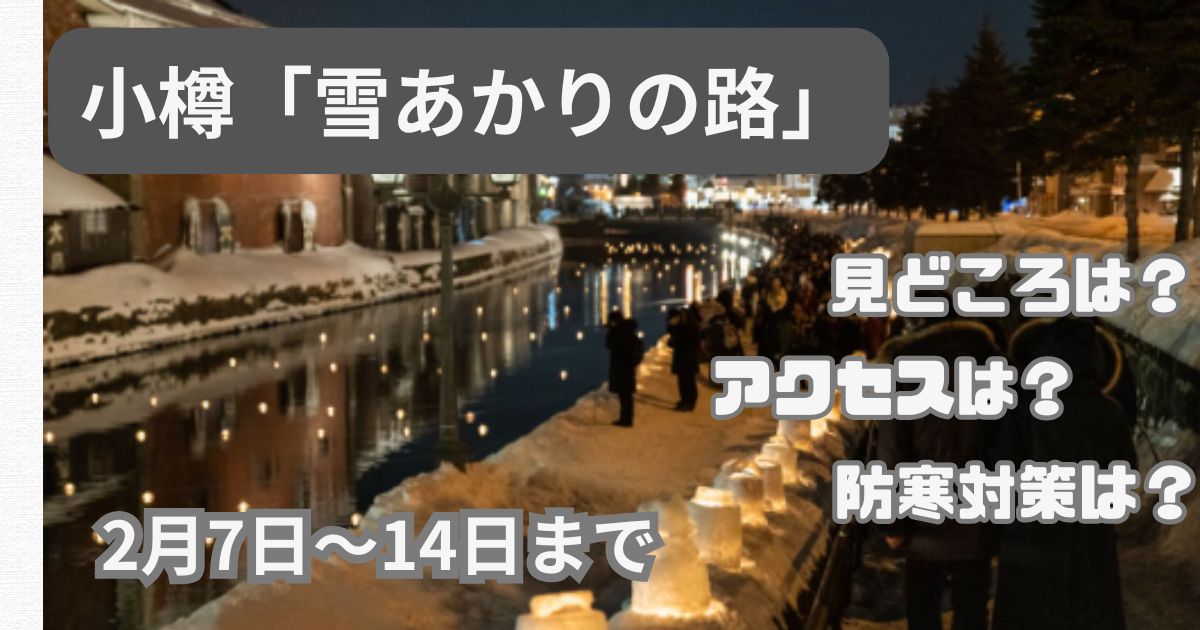


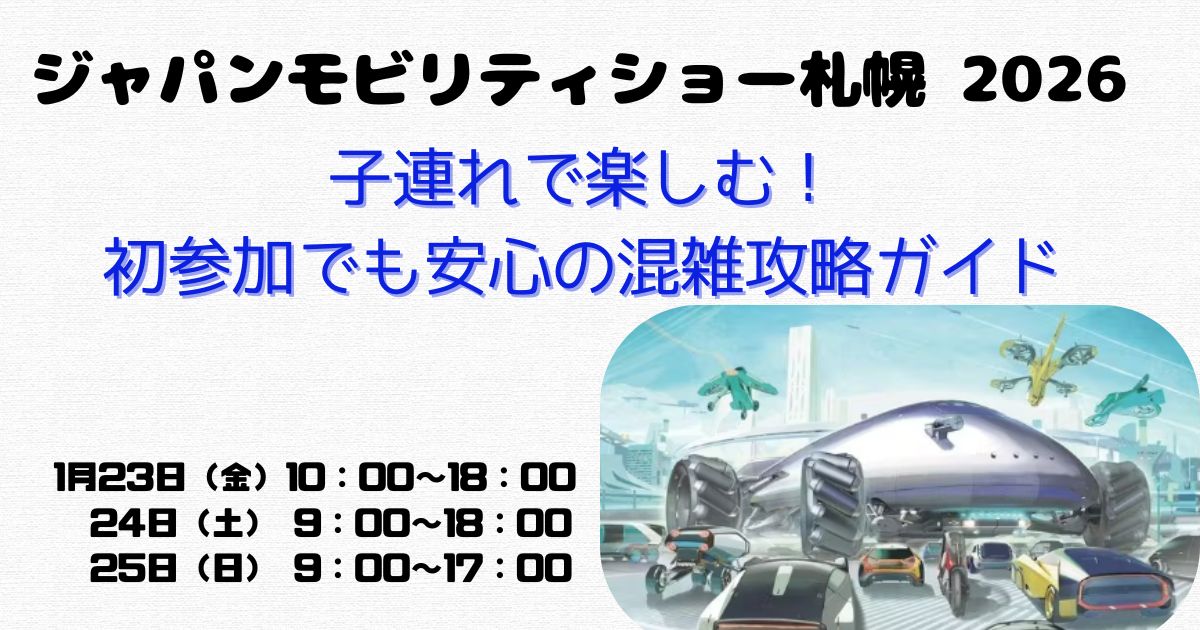
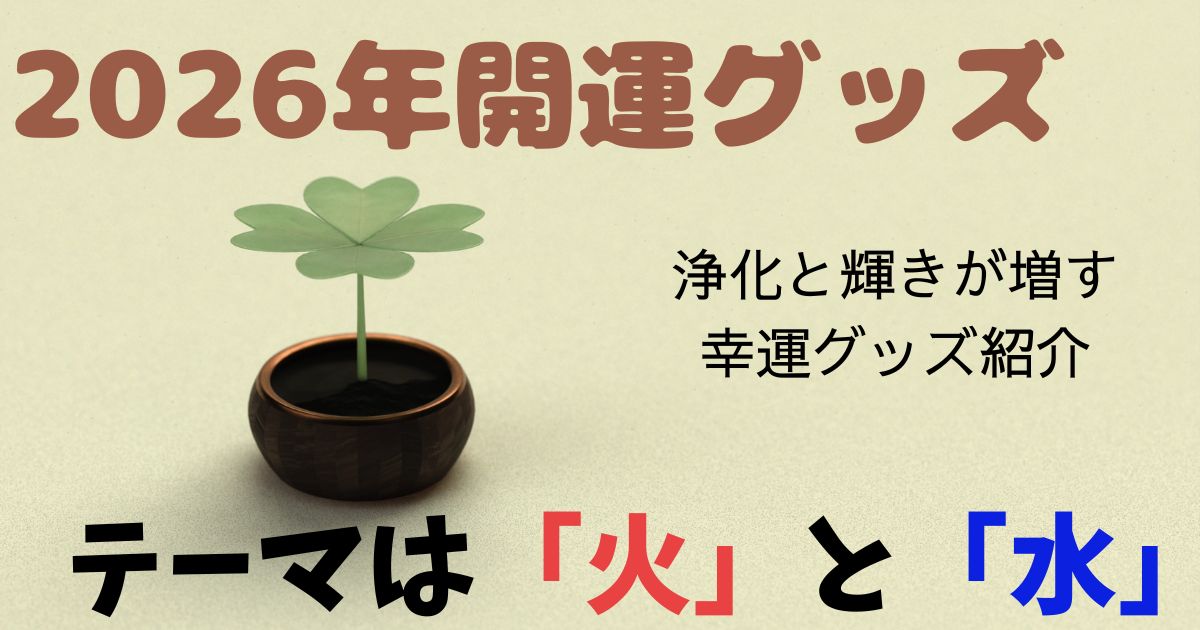



コメント